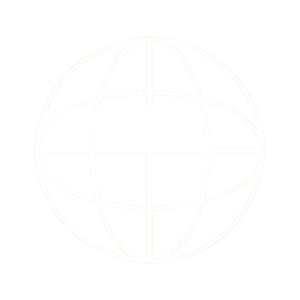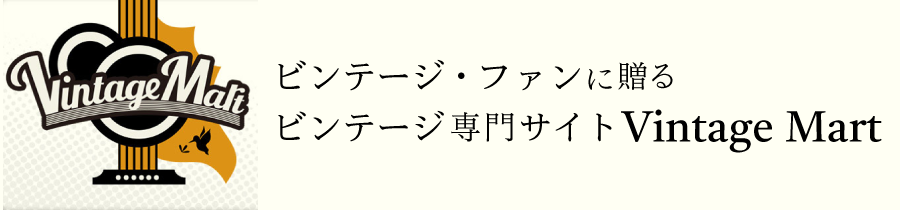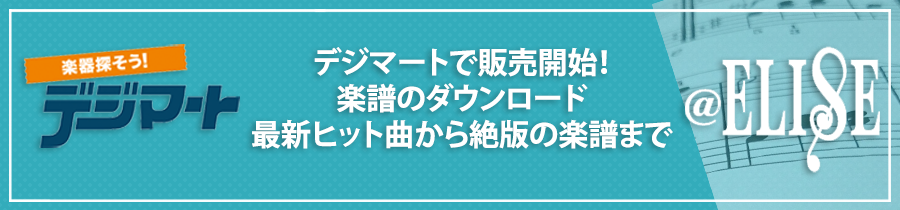国内最大級の楽器専門ショッピングモール 商品数:458,418点 店舗数:546店

ドイツの職人は海を渡り、アメリカン・ギターの祖となった

▲アメリカを代表するブランドながら、ヨーロッパのテイストも感じさせるロゴマーク。
創業者であるクリスチャン・フレデリック・マーティン・シニア(1世)が、生地ドイツからアメリカに移住してニューヨークに工房を構えたのは1833年のこと。当時のアメリカにはまだ大きな楽器メーカーは存在せず、楽器店ではヨーロッパで作られた楽器が売られていた。ドイツで既にギター製作の手腕を開花させていたマーティン・シニアだが、異国であるアメリカでは販売ルートの開拓も難しく、当初は苦労の連続であった。また、ニューヨークという大都会になじめなかったこともあり、1838年にはペンシルバニア州ナザレスの郊外に拠点を移す。ギター製作に打ち込める環境を得て再出発したマーティン社はここから飛躍的な成長を遂げ、早くも1859年にはナザレスの中心部に近いノース・ストリートに新工場を設立することになる。
新しい技術を開発することにも積極的だったマーティン・シニアは、1850年代に“Xブレイシング”を発表。ブレイシングとはトップ材の裏側にあてられる細い力木のことであり、補強材であるのはもちろんのこと、組み合わせのパターンによって音色にも大きく作用する部分である。当時は平行に並べただけのものや、扇状のパターンが一般的だったが、マーティンはX状に交差させるデザインを完成させ、輝くような高音と力強い低音を得た。音楽は生演奏だけの時代、歌の伴奏楽器はバンジョーが主流だったが、マーティンはこの革新的なブレイシングで独自のサウンドを確立し、多くのプレイヤーから求められるようになっていった。
めざましい発展を遂げたマーティン社だが、1873年、マーティン・シニアがその生涯に幕を降ろす。息子であるマーティン・ジュニア(2世)が事業を後継したものの1888年に急逝、その息子であるフランク・ヘンリー・マーティンが弱冠22歳で受け継ぐこととなる。そしてマーティン社は激動の時代を乗り越えながら20世紀へと突入していく。
現代アコースティック・ギターの標準仕様、その源流はマーティンにあり

▲写真はD-42。現代で“標準的なアコギ”といえば、おそらく多くの人がこのようなギターを連想するだろう。
1920年代当時の主流ラインナップは“O(オー)”、“OO(ダブル・オー)”、“OOO(トリプル・オー)”で、それぞれ異なるボディ・サイズですでに人気を集めていたが、当時のギターはネックとボディが12フレットの位置でジョイントされていた。マーティンに限らず、それがギターの標準的な仕様だったのである。そんな中でマーティンは14フレットでジョイントするデザインを1929年に発表する。より広くなった音域によって多彩な演奏が可能となり、その機種は“OM(オーケストラ・モデル)”と名付けられた。やがて14フレット・ジョイントがマーティン・ギターの標準となっていく。
そして1931年、かつてないほど巨大なボディを持つ“D(ドレッドノート)”を発表。名称の由来はイギリス軍の巨大戦艦である。その大きなボディがもたらす豊かな鳴りはプレイヤーの心を即座に掴み、1934年の正式発表から現在まで、時代を超えたスタンダードとなっている。現代では14フレット・ジョイントとドレッドノート・サイズのボディはブランドを問わず一般的な仕様だが、その源流はマーティンなのである。なお、マーティンがスティール弦へと移行したのは1920年代のことで、それまでは羊の腸などから作られたガット弦が使用されていた。当時まだ一般的ではなかったスティール弦だが、マーティンとの組み合わせによって新時代の音色となり、それが現代に続く音楽の流れになったようにも思えてくる。
第二次世界大戦が終結した1945年、フランク・ヘンリー・マーティンは息子のマーティン3世に会社を託す。フォーク・ミュージック台頭の時代で、需要は高まるばかりだった。さらに1950年代、エルヴィス・プレスリーなどの使用で絶大的な宣伝効果を得たマーティン社は、増大し続ける需要に応えるため、新工場を設立する。場所はやはりナザレス、シカモア・ストリート。現在は本社の社屋が建つ場所である。

▲1900年代初頭。職人達と共にフランク・ヘンリー・マーテイン(左から二人目)、C・F・マーティン3世(右から二人目)。
伝統を守りながらも未来を見据え、マーティンの歴史は続く
マーティン3世の息子であるフランク・ハーバートは1970年に会社を引き継ぎ、事業をより拡大させる。現在CEO(最高経営責任者)を務めるマーティン4世は1986年に引き継いだが、その時点でマーティン社での仕事歴は長く、幼い頃から弦の箱詰めなどをしていたという。
1990年代以降、アンプラグド・ブームを筆頭にアコースティック・ギターの人気は上昇し、有名アーティストのシグネイチャー・シリーズも発足。さらには、従来の木材とは異なる新素材を積極的に取り入れたシリーズの展開もスタートする。また、木材の調達をCITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に則って行うなど、企業改革にも積極的である。
“伝統”という側面で捉えられがちなマーティンだが、創業から6代を数える歴史をたどってみると、むしろ既成概念を打ち破る独創性にあふれたブランドであることがわかる。
「現在において“伝統”と思われているものも、昔は“革新”だったのです」
(クリスチャン・フレデリック・マーティン4世)
その“革新”がいかに的確であったかは、歴史が証明している。これからも、それは続くであろう。

▲現在のマーティン本社。併設するギター・ミュージアムには、マーティン・シニアが1834年に製作したギターも展示されている。
ボディ・サイズが違いを生む。マーティンの定番ラインナップ
マーティン・ギターのモデル名は「D-28」や「OOO-42」などで知られるように、英字と数字の組み合わせである。 基本的な読み方としては、まずハイフンの前につく英字はボディ・サイズを示したもの。後述する各サイズの数値はボディ外周が最も広い部分(ギターを立てた状態でブリッジ下方あたり)の左右幅なので、それぞれの大きさをイメージしてみてはいかがだろうか。
そしてハイフン後の数字は“スタイル”と呼ばれるもので、仕様材の種類やグレード、装飾の違いなどが示されている。例えば、共に定番モデルである「D-28」と「D-45」を比較した場合、ギターとしての基本的構造は同じだが、番号が大きい「D-45」のほうが様々な部分でグレードが高いのである。このスタイル・ナンバーが大きいほど高額にもなるが、あくまでもグレードであってサウンドの差ではないので、くれぐれも誤解しないでいただきたい。
マーティンの全ラインナップを見渡すと実に様々なモデルがあるが、今回はスタンダードなタイプに焦点をあててみた。ボディ・サイズとスタイルを吟味して、自分の好みにあったマーティンを見つけてもらいたい。
D(ドレッドノート)
定番「D-28」「D-45」等で知られるサイズ。15 5/8インチ(396.9ミリ)幅の大柄なボディがもたらすサウンドは力強く、ヴォーカリストやソングライターにも人気だ。ネック・スケールは25.4インチ(645.2ミリ)。ヴィンテージ・テイストを高めた「HD」シリーズにも注目。
OOO(トリプル・オー/別名「オーディトリアム」)
「OOO-28」「OOO-42」等で支持を集める定番サイズ。ボディ幅は15インチ(381ミリ)、ネック・スケールは24.9インチ(632.5ミリ)だ。ブルース・プレイヤーからの信頼も厚く、近年ではECシグネイチャー・モデルでも注目を集めた。1902年までさかのぼれる伝統性も魅力。
OM(オーケストラ・モデル)
ボディ幅はOOOと同寸でありながら、Dのネック・スケールを持つことから分類されている。この仕様ならではのサウンドと弾き心地には独特の魅力があり、根強いファンを生みだしている。“通好み”的な存在だが、言うまでもなく正統マーティン・サウンドを放つ。
OO(グランド・コンサート/別名「グランド・オーケストラ」
比較的小柄なボディ幅は14 5/16インチ(363.5ミリ)。いわゆるクラシック・ギターと同サイズで、指弾きプレイヤーからの人気も高い。ネック・スケールは24.9インチ(632.5ミリ)。起源を1877年までさかのぼることができるという伝統性も魅力のひとつ。